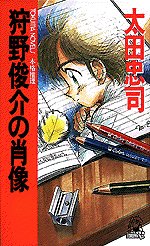 徳間ノベルズ刊
徳間ノベルズ刊定価800円
ISBN4-19-850352-4
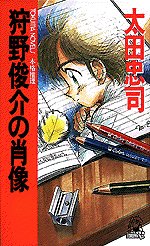
定価800円
ISBN4-19-850352-4
金糸雀(カナリア)は、もう鳴かない
1
その月曜の朝、遠島寺美樹はいつもより早く家を出た。
二学期が始まって二週間あまり、夏休みの間に抜け落ちてしまった時間の感覚もようやく戻ってきていた。それでも、たまの早出がある日は、起床してから家を出るまで慌ただしい時間を過ごさねばならないのが、少々辛かった。
特にその日のように、本来は自分が早出をする番ではないのに、他人の都合でそうしなければならないとなると、いくらかは億劫さを感じずにはいられない。
しかし美樹は、そんな後ろ向きな気持ちを心の奥に押さえ込んで、学校への道も歩きはじめた。代役を買って出たのは自分自身だったからだ。
美樹の家から学校までは、徒歩で二十分ほどだった。途中で小さな公園を突っ切り、細い路地と大きな車道が交差する十字路を通る。
その十字路で美樹は、一旦歩みをとめた。そしていつものように車道のほうに眼をやった。小さな乗用車が路肩に停められている以外、人の気配もなかった。
「あ、そっか……」
美樹は舌打ちをした。いつもより三十分早くこの場にきたことを、そのときだけ、すっかり忘れていたのだ。
「……馬鹿みたい」
彼女は苦笑まじりに呟くと、再び歩きはじめた。
朝の陽射しは、少しずつ秋の気配を増してきていた。半袖の腕や頬に触れる風も、いくらか涼しく感じられる。しかし空を見上げれば巨大な積乱雲が伸び上がって、夏が完全に過ぎ去ってはいないことを告げていた。たぶん昼過ぎ頃になれば暑くなってくるだろう、と美樹は思った。
学校の校門が見えてきた。周囲を取り囲む塀と同じ赤煉瓦で造られた門柱には、「新星中学」という文字を刻印した銅板が埋め込まれている。彼女が今年の四月から通っている学校だ。重い鉄の門は、すでに開かれていた。
校庭では野球部と庭球部の部員たちが、早朝の練習をはじめていた。美樹は彼らの邪魔にならないよう、校庭の隅を通って校舎に向かった。
南校舎一階の端から四番目の部屋が、美樹のいる一年四組の教室だった。まだ誰も来ていないようだった。
自分の机の上に鞄を置くと、美樹はすぐに教室を出た。
通路を渡って北校舎へ向かった。校舎一階の端に用務員室がある。
「おはようございます」
美樹は声をかけてから扉を開いた。
用務員は長瀬という六十歳すぎの男だった。
「おはよう。今日も早いね」
長瀬は口に持っていきかけていた湯飲みを置くと、柔和な笑みを浮かべた。そして部屋の壁に掛けてある木箱の錠を外すと、蓋を開けた。そこには学校内の各施設の鍵がまとめて保管されている。
長瀬はその中から「禽舎」と大きく書かれた木札のついた鍵を取り出した。
「ほい」
「ありがとうございます」
美樹は鍵を受け取ると、もう一度丁寧に頭を下げて用務員室を辞した。
南校舎と北校舎の間に中庭がある。美樹はその中庭に足を踏み入れた。
「あれ? 遠島寺さん?」
不意に名を呼ばれ、美樹はふりかえった。南校舎と北校舎を結ぶ通路に、顔見知りの男子生徒が立っていた。
「あ、里山先輩」
「どうしたの? こんなに早く」
里山と呼ばれた男子生徒は、ゆっくりと美樹のほうに歩いてきた。二年生の中でも長身の部類に入るであろう里山は、不思議そうな表情で彼女を見ていた。ほっそり
した知的な顔立ちに、縁のない眼鏡が似合っていた。
年上であるせいかもしれないが、美樹にはそんな彼がとても大人びて見えた。
「あ、あの……今朝は早出だったんです。飼育部の……」
返答が妙にしどろもどろになってしまい、美樹は内心焦っていた。
「飼育部の? だって君は、土曜日も早出で来てたんじゃなかったの? たしか今日は堀内の当番じゃ……」
「はい、そうなんですけど、今日は代わりなんです。堀内先輩の」
「堀内、どうかしたの?」
「昨日の夜、電話があったんです。風邪で熱がひどくて学校に行けそうにないから、早出を代わってほしいって」
「へえ……そうなのか」
里山は納得したように頷いた。
「先輩は、どうしてこんなに早く学校に来たんですか」
美樹が尋ねると、里山は薄く微笑んだ。
「新聞を締切に間に合わせるためさ。週に何回かは早めに学校へ来て仕事をしないといけないんだ。学校じゃ徹夜で新聞編集をさせてはくれないからね」
「そうなんですか。大変ですね」
里山龍夫は新聞部の部長だった。部で制作している「新星新聞」は月刊の学内新聞で、校内の行事や出来事、生徒や倶楽部の紹介などを掲載している。
「いや、僕らより飼育部のひとたちのほうが大変だと思うよ。夏休みや春休みにも交代で出てこなきゃいけないし、こうやって早出もしなきゃならないしね。よく続けられるもんだと感心してるんだ」
「そんな……」
美樹は頬が熱くなるのを感じていた。
「どうして飼育部みたいな大変な倶楽部に……ああ、この質問は先週したんだよね?」
「ええ……あの記事、まとまったんですか」
「いや、それを今朝、やりにきたのさ」
里山は苦笑を浮かべる。
先週の土曜、美樹は里山の取材を受けていた。新聞に載せる倶楽部紹介の記事のために、彼女が部を代表して活動内容について話したのである。入ったばかりの、ましてや部長でもない彼女が取材を受けることになったのは、たまたまその日が彼女の当番日であったからだった。里山の意向で美樹は実際に禽舎での仕事を見せながら、彼の質問に答えたのだった。
里山に飼育部に入部した動機を訊かれたとき、美樹はこう答えた。
「もともと動物が好きだったからです。それと家で、生き物を飼えないから」
美樹は母方の祖母である広瀬幸子とふたり暮らしをしていた。その幸子が生き物を飼うことを好まず、美樹はいまだかつて自分で動物を世話したことがなかったのだった。だから中学に入ると、迷わず飼育部を選んだのである。
入部してみると他の部員たちも同じように、生き物が飼いたくても飼えない状況にある者ばかりであることがわかった。当然そうした生徒の数はそれほど多くはないので、飼育部員の数も三学年合わせて五人という、いささか寂しいものだった。その分、部員たちの負担も大きくならざるをえない。今朝のようにひとりが病欠すると、誰かが続けて早出当番をしなければならなくなるのだ。
「でも、いいんです。生き物と一緒にいるのが好きですから」
美樹は自分がそう答えたことを思い出した。少しばかり格好をつけすぎた言いかただったような気がして、美樹はまた赤面してしまった。
「じゃあ、あたし、行きます」
美樹は自分の狼狽を気取られないよう頭を下げると、急いで里山から離れた。
中庭の一番東の端に、飼育部の禽舎があった。長さ三メートル、幅二メートル、高さ二メートルほどの、結構大きな建物であった。
その禽舎の中で現在、金糸雀(カナリア)が四羽飼われていた。禽舎の大きさに比べると飼育数が少なすぎるのだが、先輩の話によると以前はもっと色々な種類の生き物がたくさん飼われていたのだという。中にある池はそのときの名残で、昔は亀を飼っていたらしい。しかし飼っていた生き物が死んだ後、あらたに補充されることがなかったせいで次第に数を減らし、現在のような寂しい状況になってしまったということだった。
飼育部ではこれまでにも何度か飼育する生き物を増やしたいと申請したのだが、色よい返事はもらえなかった。どうやら学校としては、これ以上動物を増やすつもりはないようだった。小学校ならともかく、中学で飼育禽舎があるのは、この街の中学ではここだけらしい。
「先生がたは、それを名誉とは考えずに、恥だと思ってるらしいのよね」
部長が一度、美樹にそう言ったことがある。
「だから早いとこ禽舎をなくして、飼育部もお取り潰しにしたいのよ。一応、今いる鳥たちが元気なうちは、そんなことはしないって約束は取りつけてあるんだけど……学校側の目的が達成されるのも、そんなに遅くはならないかもしれないわね。あの子たち、そろそろ寿命だし」
金糸雀がいなくなったら、飼育部は潰される。その言葉を思い出すたびに、美樹の胸にはしこりのような喪失感が生まれてくるのだった。
彼女はそんな嫌な気分を振り払うように、禽舎に向かって駆けた。
が、禽舎が近づくにつれて、美樹の歩みは遅くなっていった。何かわけのわからない違和感が、金網を巡らせた禽舎のほうから漂ってくるように思えたからだ。
何だろう、何が変なんだろう……美樹は訝しみながら禽舎に近づき、そしてとうとう足をとめた。違和感の正体に気づいたのだ。
鳥の声が、聞こえない。
いつもなら、禽舎に近づくにつれて金糸雀たちの声が耳に届くはずだった。ここで飼われているのは特に鳴き声を楽しむために品種改良された「鳴き金糸雀」と呼ばれる種類のもので、いつも麗々しい歌を聞かせてくれている。しかし今、禽舎からは静寂しか伝わってこない。
美樹は眼を凝らした。そして次の瞬間、その眼を大きく見開いた。
金糸雀の姿が、なかった。
美樹は金網に顔を押しつけんばかりにして、中を覗き込んだ。やはり、どこにも姿が見えなかった。
禽舎の中には巣箱が掛けてある。その中に入っているのなら、見えなくてもどうということはない。しかし今までの経験からすると、この時間に金糸雀たちが巣箱に引き篭ったままでいることは、一度もなかった。いつも飼育当番が来るのを待ちかねていたように止まり木の間を飛び回り、騒々しく鳴きつづけているのだ。
「……どうしたのかしら……?」
美樹は思わず呟いていた。早く中に入って確かめねばならない。美樹は禽舎の鍵を握りしめた。
「遠島寺さん」
突然声をかけられ、美樹は危うく声をあげそうになった。
「あ、驚かせてごめん」
里山だった。
「ちょっと例の記事で補足したいことがあったんで、もう一度禽舎を見せてもらいたいんだけど……あれ、どうかしたの?」
美樹の様子が変であるのに気づいたのか、里山は首を傾げた。
「僕、驚かせすぎちゃったかな?」
「いえ、そうじゃないんです。ただ……」
美樹はそれ以上答えることができなかった。自分の不安がただの思い過ごしなのかそうでないのか、確信が持てなかったからだ。
「ちょっと……待ってくださいね」
美樹はそう言うと禽舎の裏へ廻り、出入口の扉に掛けられた南京錠に鍵を差し込んだ。自分の指の動きがもどかしかった。
「遠島寺さん、変だよ」
後からついてきた里山が怪訝そうな口調で言った。美樹はそれにも答えず、苦労して錠を外すと扉を開けた。
出入口と鳥たちの住処との間には鉄板で仕切られた、準備室という名の小さな空間があった。いきなり出入口を開けて鳥が外に逃げ出さないようにするために設けられたもので、鳥の飼料や掃除道具等の保管場所も兼ねている。金糸雀の住処に入るには、出入口の向い側にある扉を開けなければならない。その扉には閂が掛っていた。美樹は閂を外し、中に入った。
静かだった。やはり鳴き声はしない。美樹は背伸びをすると、巣箱の中を覗き込
だ。
金糸雀はいなかった。
「どうしたんだ?」
里山が入ってきた。
「……いないんです」
美樹は自分の声が強ばっているのに気づいた。
「いない?」
「金糸雀が……いないんです」
「なんだって!?」
里山も驚いたようだった。
「本当に? だって土曜日にはちゃんといたじゃないか。どこかに隠れてるんじゃ……」
里山は長身なので、背伸びをしなくても巣箱の中を覗きこむことができた。
「……たしかに、いないな。こいつはいったい……」
「どうしたんだろ……」
美樹は途方に暮れながら、禽舎の中を見渡した。
その眼が、里山の足元でとまった。
「里山先輩……足……」
「え?」
里山がふりかえる。
「足……足……」
里山は自分の足元に眼をやった。そして、
「わっ!」
自分の踏んでいるものを見て飛び上がった。
黄色い羽根が、固まって落ちていた。
「金糸雀の……羽根?」
美樹は床にしゃがみこんだ。
「そうです。金糸雀の羽です。でも、自然に抜け落ちたんじゃない……」
「え?」
里山も美樹の横に腰を下ろすと、羽根に眼を近づけた。
羽根は数本がよじれるようにしてくっついていた。そして根元のあたりに、赤い染みが付着していた。
「……血」
美樹は自分の言葉に身震いした。
「遠島寺さん、先生を呼んできたほうがいい」
里山が落ち着いた声で言った。
「先生、ですか」
「うん、そのほうがいいよ。ここは僕が見張っているから、すぐに」
「……はい、わかりました」
美樹は立ち上がった。と、不意に眼の前が真っ白になって歪んだ。
「あ……」
思わず膝が折れる。
「どうしたんだ!?」
里山が倒れそうになる美樹の体を支えた。
「……ご、ごめんなさい。ちょっと立ち眩みが……」
美樹はあわてて体を起こした。
「もう、大丈夫です。あたし、先生を呼んできます」
動転しながらも彼女は、里山を置いて禽舎から飛び出した。しかし北校舎に向かいかけたところで、またも眩暈に襲われた。金糸雀の消失、血のついた羽根、立ち眩み、そして里山に倒れかかってしまったこと。一度に起きた出来事が、美樹の平衡感覚を歪ませていたのだ。
よろよろと歩きかけて、北校舎の壁に手を突いた。
「……どうして……何が起きたの……?」
声にならない声が、美樹の口から洩れた。
(この続きは、買って読んでね)